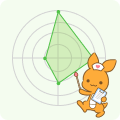周産期母子医療センター認定病院で働く
周産期母子医療センター認定病院には医師が多く、最新の設備が整っている所が多いため、ハイリスクなお産が多い点が特徴。
大学病院や総合病院の一部(公的病院、赤十字病院など)が認定されています。ハイリスクなお産に携わることで知識をつけたい、異常を見極める目を養いたいという方にオススメの職場です。
- Q. 周産期母子医療センターでは分娩介助の機会が少ないと聞きましたが…
-
A. 認定外の病院と比べ、通常分娩件数自体が少ないです。
周産期母子医療センターは、設備の特徴上ハイリスクなお産がほとんど。そのため、分娩はほぼ全て医師が主体で行います。助産師の主な仕事は医師のサポート業務となり、実際に取り上げる機会は、数少ない通常分娩時に限られます。
ただし通常分娩の介助は、主に若手助産師の役目。つまり助産師としての年次が上がるほど、取り上げのチャンスは更に減少する傾向にあります。
また、縦割りの業務となる病院が多い点も、分娩介助の機会が減少する原因のひとつです。助産師は産科に配属された後、病棟か外来のどちらかに割り振られます。実際に行う業務内容は、その後更に細かいフローごとに縦割りされるケースが多いため、母乳指導や母体指導のみを行う助産師も数多く存在します。
面接時には、入職した場合に何の業務を行う可能性が高いのか、またどの業務を行いたいといった希望をきちんと伝えておくと良いでしょう。
- Q. ハイリスクなお産に対する知識を学びつつ、分娩介助もできる病院はありませんか?
-
A. 院内助産院が併設されている周産期母子医療センターであれば、通常分娩の介助もできます。
通常分娩件数自体が少ない周産期母子医療センターですが、院内助産院を併設することで通常分娩の取り上げを行っている病院もあります。
院内助産院とは、その名の通り病院内に設けられた助産院のこと。基本的に出産フローの全てを助産師が主体となって行いますが、異常事態が起こった際はすぐに病院内の医師と連携を組むことができます。いわば、助産院と病院のメリットを掛け合わせた施設です。
こうした施設が併設されている周産期母子医療センターであれば、分娩介助の機会を失わずに働き続けることも可能です。
上記はあくまで、各職場の傾向を示したものです。具体的にどんな職場があるのか、自分の住んでいる地域の求人傾向はどうなっているのか…
気になることはぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。